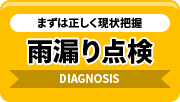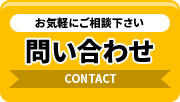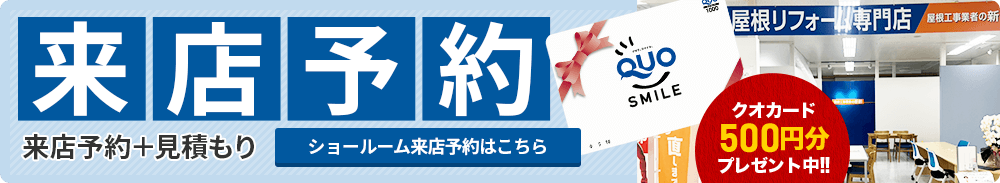積雪×塩害エリアでの屋根材選び:耐風・耐食・メンテ周期の指針
2025.10.15 (Wed) 更新

新潟市の皆さんこんにちは!
雨漏りなら屋根工事・雨樋工事の匠、新潟市の屋根業者!新創へ!
目次
代表の帆刈です!
屋根は住まいの「傘」のように、毎日の風雨や雪を静かに受け止めてくれています。だからこそ、見えない部分ほど誠実に施工し、定期点検を怠らないことが大切なのです。屋根材のグレードよりも、正しい納まりとメンテ体制が整っているかどうか――。それが、20年後の安心を左右します。
今回のお役立ちコラムでは、積雪地や海沿いなど、気候の厳しい地域で屋根材を選ぶ際の「正しい基準」を整理します。結論から言えば、最適な屋根は「強い屋根」ではなく「地域と相性の良い屋根」です。
積雪、強風、潮風といった複合的な自然環境においては、耐風性・耐食性・メンテナンス周期のバランスをとることが何より大切ですよ。この記事を読めば、屋根材の特徴だけでなく、“長く安心して使い続けるための考え方”がわかるはずです。
▼合わせて読みたい▼
窓枠まわりの結露に悩む方へ|外壁側からできる防止対策と施工業者選び

出張現地見積無料!お気軽に問い合わせください
緊急のご相談大歓迎!強引な営業は一切致しませんので、お気軽にどうぞ!
積雪×潮風エリアの屋根に起こりやすい“複合劣化”とは

気候条件が厳しい地域ほど、屋根は多方向からのストレスを受けています。
- 雪の重み
- 風の巻き上げ
- 潮風による腐食
- 凍結と融解の繰り返し
それらが重なって起きるのが、いわゆる“複合劣化”です。ここでは、どんな現象が屋根に起きやすいのかを見ていきましょう。
積雪荷重+強風による構造的ストレス
屋根は、雪の「重さ」に耐えるだけでなく、風による「浮き上がり力」にもさらされています。とくに、積雪地域では、風が吹き抜ける方向と屋根勾配の関係によって、棟や軒先で“めくれ上がり”が発生しやすくなるのです。
雪が積もることで屋根全体が押され、さらに突風で部分的に持ち上がります。この繰り返しが板金の浮きや釘抜けの原因となるのです。また、地域別に設定されている「風速基準」と「積雪荷重基準」は、それぞれ別の構造設計指針に基づいています。
つまり、どちらか一方の基準を満たしていても、もう一方が弱ければ屋根の寿命は短くなってしまうのです。このため、設計段階で“風+雪”両方に耐えられる仕組みを組み込むことが求められます。
塩害・凍結・湿気による素材腐食の進行
海沿いや豪雪地帯では、「サビ」「白サビ」「塗膜割れ」といった腐食ダメージが複合的に進みます。とくに金属系屋根材では、潮風に含まれる塩分が水滴に付着し、乾燥・湿潤を繰り返すことで電食(異種金属腐食)が発生します。一度発生したサビは内部に進行しやすく、塗膜の下で静かに広がっていくのです。
また、凍結と融解を繰り返すと、表面の塗膜が収縮と膨張を繰り返し、やがて微細なクラック(ひび割れ)を生みます。そこから再び水分が入り、腐食が加速するという悪循環です。塩害+凍害の“ダブルパンチ”は、表面処理の品質やメンテナンスのタイミングによって差が大きく出る部分です。このエリアでは「素材」だけでなく「表面仕上げ」の選定がとても重要になります。
耐風・耐食・断熱を両立させる屋根材と仕舞い
どんな屋根材にも得意・不得意があります。重要なのは「耐風・耐食・断熱」の3つをバランス良く成立させることです。たとえば、強度だけを求めて金属を厚くすれば断熱性が下がります。断熱材を増やしすぎれば通気が悪くなり、結露が起こるのです。
この章では、素材の特徴と“仕舞い設計”の考え方を整理します。
金属系屋根材の比較|ガルバリウム・SGL・ステンレス
代表的な金属屋根材である「ガルバリウム鋼板」は、アルミと亜鉛の合金層で覆われた構造になります。耐食性に優れていますが、海沿いでは塩分による腐食が進みやすく、メンテ周期が短くなりがちです。その弱点を補ったのがSGL(次世代ガルバリウム)です。
マグネシウムを加えることで防サビ性能が向上し、とくに塩害地域では効果を発揮します。表面の「マグネシウム被膜」は、腐食部を自ら再生する特性があり、従来品より寿命が約1.5倍延びるという実測データもあります。
一方、ステンレスは耐食性・耐熱性ともに非常に高く、海岸線近くでもサビにくい素材です。ただし、熱伝導率が高いため、夏場の熱を屋根裏に伝えやすく、断熱層の設計が不可欠です。さらに、コストも他素材より高いため、全体予算とのバランスを検討する必要があります。
塗装仕上げも耐久性を左右する大きな要素です。同じガルバリウムでも、フッ素塗装とポリエステル塗装では“塗膜寿命”が倍以上変わります。このため、塗料グレードを含めて選ぶことが、トータルでのコスパにつながります。
積雪地での“仕舞い設計”とメンテナンス目安
素材だけでなく、屋根の「仕舞い(おさまり)」も耐久性を決定づけます。仕舞いとは、屋根のパーツとパーツをどうつなぐか・どう終わらせるかという“構造の仕立て”のことです。積雪地では、雪止め金具・棟包み・軒先板金の強度と配置がとても重要です。風と雪の流れを読むように設計することで、局部的な負荷を分散できます。
屋根勾配によっても滑雪性は大きく変わります。緩勾配では雪がとどまりやすく、荷重が長時間かかるため、下地の強度確保が必須です。逆に急勾配では雪が滑りやすく、落雪による被害を防ぐための雪止めが欠かせません。
メンテナンスの目安としては以下が参考になります。
- 10年:塗膜点検と軽補修
- 20年:棟・雪止め金具の交換
- 30年:再塗装または葺き替え検討
これを怠ると、塗膜劣化から下地腐食へと一気に進行するケースもあります。「まだ大丈夫」と思っているうちに見えない部分で劣化が進んでいる――そんな事例を数多く見てきました。雪国では、冬の間に屋根の上で起こるトラブルのほとんどが“想定外の荷重”です。屋根の形状が少し変わるだけで、雪の滞留パターンが変わり、特定の軒先や谷部に集中します。
とくにリフォームで勾配や素材を変えた場合は、以前と同じ雪止め配置では対応できないこともあるのです。一見小さな部材でも、仕舞いの一つひとつが安全性を左右するのです。現場では、屋根上での雪解け水の流れ方を模型で再現して、金具位置を検討することもあります。
▼合わせて読みたい▼
雪国アパートの屋根メンテ:雪止め・落雪・凍害の実践ハンドブック

出張現地見積無料!お気軽に問い合わせください
緊急のご相談大歓迎!強引な営業は一切致しませんので、お気軽にどうぞ!
気候適合型の屋根選びチェックリスト

地域に合わない屋根材を選ぶと、どんなに高性能でも本来の力を発揮できません。たとえば、雪国でフラット屋根を採用したり、海沿いでポリ塗装を使ったりといったようにです。施工技術が良くても、そもそもの「気候適合性」がズレていれば早期劣化は避けられません。
ここでは、地域ごとに考えるチェックポイントを整理します。
判断の3軸「地域・材質・施工法」で考える
屋根選びの基本軸は「地域」「材質」「施工法」です。この3つを掛け合わせることで、最も劣化しにくい組み合わせが見えてきます。
- 積雪多い内陸部→SGL+立平葺き(雪滑りと耐風両立)
- 塩害強い海岸部→ステンレス+瓦棒葺き(防サビ+防水性重視)
- 風が強い山間部→ガルバ+断熱一体型(金属の軽さを活かす)
また、地域の気候データを基に「積雪深」「最大風速」「塩害指数」を一覧にまとめることで、施工計画の段階から適合性を確認できます。この“気候適合表”をつくるだけでも、将来のメンテ費用を大幅におさえられる可能性があります。
屋根リフォーム時に確認すべき施工項目
リフォームで屋根を張り替える際は、表面材よりも“下地”が重要です。屋根下地が湿気で傷んでいれば、どんな高級屋根材をのせても意味がありません。とくに通気層(換気スペース)が確保されているかを必ず確認しましょう。
熱や湿気を逃がす構造があるだけで、塗膜や下地の寿命は2倍以上変わることもあります。メーカー保証の条件も、施工の良し悪しに直結します。「どの下地材を使うか」「どの地域区分で試験された製品か」を確認せずに契約してしまうと、万が一の際に保証対象外となるケースもあるのです。
また、地元業者の強みは“地域特性”を肌で知っているということも覚えておきましょう。カタログ上の数値だけでは測れない“風の癖”や“雪の流れ方”を熟知していることが、何よりの安心材料です。

出張現地見積無料!お気軽に問い合わせください
緊急のご相談大歓迎!強引な営業は一切致しませんので、お気軽にどうぞ!
FAQ|積雪地・塩害地域の屋根選びについてよくある質問

積雪地や海沿いのように厳しい環境では、素材の選択やメンテ周期について多くの質問をいただきます。
ここでは実際にお客様から寄せられる代表的な質問にお答えします。
Q.海沿いでガルバリウム鋼板は使っても大丈夫?
A.条件付きで可能です。海からの距離が500m以内ならSGLやステンレスが推奨されます。どうしてもガルバを使う場合は、厚めの塗膜仕様+定期洗浄で塩分除去をおこなうことが重要です。
Q.SGLとガルバリウム、どちらが長持ちしますか?
A.SGLの方が平均で1.3〜1.5倍長寿命です。マグネシウム層が腐食を自己修復するため、塩害地や多湿地ではとくに効果があります。
Q.雪止めは必ず設置した方がいい?
A.勾配や隣接環境によります。歩道・隣家が近い場合は必須です。雪庇防止ネットやヒーター併用でより安全性が上がります。
Q.塩害地域では屋根色も影響しますか?
A.はい。濃色は熱を吸収しやすく塗膜疲労を早めます。明るめの色を選ぶことで温度上昇をおさえ、塗膜寿命を延ばせます。
Q.どのくらいの周期で点検・再塗装をすれば安心?
A.一般的には10年ごとの点検を推奨しています。沿岸部では7〜8年サイクルで早めの塗膜再生をおこなうと長持ちします。

出張現地見積無料!お気軽に問い合わせください
緊急のご相談大歓迎!強引な営業は一切致しませんので、お気軽にどうぞ!
“地域適合”が屋根の寿命を決める!新潟県で困ったら新創へ

屋根材選びの正解は「全国共通」ではありません。雪、風、潮風――地域ごとの気候特性を見極め、それに合わせた素材と仕舞いを選ぶことが大切です。それが、結果的にメンテナンスコストをおさえ、長く安心できる住まいを守ります。
「強い屋根」ではなく、「地域に馴染む屋根」。その選び方が、結果として“強く長持ちする家”をつくります。屋根は普段の暮らしの中では意識しづらい場所です。だからこそ、“少しの違和感”を放置せず、早めに点検・相談することが安心につながります。
新潟市の屋根工事業者の新創は、出張現地見積無料ですのでお気軽にお問い合わせください。イオン新潟東店3階には、屋根工事がイメージできる体験型ショールームもございます。ご来店予約もお気軽にどうぞ。

出張現地見積無料!お気軽に問い合わせください
緊急のご相談大歓迎!強引な営業は一切致しませんので、お気軽にどうぞ!
▼合わせて読みたい▼
屋根工事業者の新創|新創が選ばれる理由