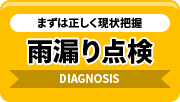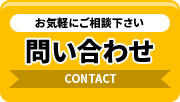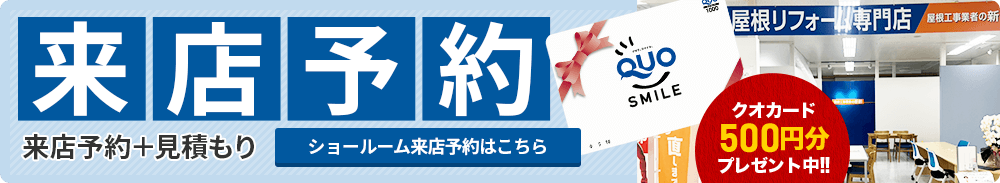自分でできる外壁内結露の点検方法|必要な道具と見逃しがちなサインとは
2025.07.11 (Fri) 更新

新潟市の皆さんこんにちは!
雨漏りなら屋根工事・雨樋工事の匠、新潟市の屋根業者!新創へ!
- 「最近、壁紙が浮いている」
- 「冬になると壁がいつも冷たい」
と感じたら、外壁内部で結露が起きているサインかもしれません。
外壁の内部結露は雨漏りとは違って静かに進行するため、気づかぬうちに柱の腐朽や断熱性能の低下、カビ被害を引き起こす恐れがあります。放置すると家の資産価値を下げ、最悪の場合は健康被害にもつながるため危険です。
しかし「すぐに業者を呼ぶのは費用面で不安」「自分で確認して現状を把握したい」と考える方も多いでしょう。その際は、セルフ点検をすると被害拡大を防げるかもしれません。今回のお役立ちブログでは、DIY志向の施主向けに自分でできる外壁内結露の点検方法や道具、チェックポイント、予防策などをお話しします。
目次
外壁の内部結露について知ろう!基本を押さえることが点検の第一歩
結露とは、空気中の水蒸気が冷えた面に触れることで、水滴となって現れる現象です。冬場を中心に室内の暖かく湿った空気が外壁内部に入り、外気で冷えると結露が発生します。断熱性能が不十分な家や隙間風が多い家で起こりやすいのが特徴です。
また、結露と似た症状で雨漏りがあります。どちらも壁紙の剥がれやカビの発生を招くため症状は似ているものの、雨漏りは外部から水が直接浸入するのに対し、結露は室内の湿気により、外壁内部で水滴化する症状であるため異なります。
さらに、室内の生活環境で発生頻度が変わる点も特徴です。たとえば、室内で洗濯物を干すことが多かったり、換気が不十分な環境だったりすると湿度が慢性的に高くなるため、外壁内部で結露が発生しやすくなります。
壁内結露の被害例
壁内結露の被害例として、壁紙の浮きや剥がれ、黒ずみの発生などが挙げられます。クロスの下で結露が繰り返されると接着力が低下して、剥がれや膨らみが現れるため危険です。
また、壁内の結露により断熱材が濡れ続けると、断熱性能が低下して冷暖房効率が落ちる場合もあります。湿気が含まれた断熱材は本来の性能を発揮できず、結露がさらに進行する悪循環を生み出すため被害は拡大する一方です。
見逃しがちな外壁の内部結露の兆候は場所によって違う!何が起こる?

結露は壁内で静かに進行する分、外からは気づきにくいのが特徴です。しかし、いくつかの兆候を知っておくと早期発見できます。
ここでは、
- 室内で見逃しがちな結露の兆候
- 外壁側で見逃しがちな結露の兆候
を中心にお話しします。
室内で見逃しがちな結露の兆候
壁紙の浮きや剥がれは、内部結露が疑われる代表的な兆候です。窓周辺だけでなく壁の中央部分で剥がれが起きている場合も気を付けましょう。クロスの剥がれは湿気が内部から押し上げているサインであり、壁内結露や断熱材の濡れによる湿度上昇が原因となっている可能性があります。
また「壁紙の黒ずみ・カビ臭・手で触れた際に感じた湿気」がある場合も結露の兆候です。毎年同じ箇所で水滴や黒ずみが繰り返される場合も、壁内の温度差による湿気滞留の可能性があるため、疑った方が良いでしょう。
外壁側で見逃しがちな結露の兆候
塗装の色ムラや変色、白華現象(エフロレッセンス)は内部結露の可能性があります。さらに、「サイディングの浮き・反り、モルタル塗膜の膨れ、窓周辺や目地コーキングのひび割れ・剥離」が見られた場合も、内部結露かもしれません。
また、晴れの日が続いているのに乾きにくい場合も、結露を起こしている可能性があるため要注意です。
自分でできる外壁の内部結露の点検方法を知ろう!何の道具が必要?

「専門業者に依頼する前に、自分で今の状況を知りたい」方にセルフチェックの方法をお話しします。チェック時は、次の道具を用意しましょう。
- 非接触温度計
- 湿度計
- 点検用ライト
- マスキングテープと油性ペン
- スマートフォン
非接触温度計は壁面の温度差測定に使用し、湿度計は湿度管理に役立ちます。さらに、点検用ライトはクロス浮き・カビの状態を詳細確認する際に便利です。また、マスキングテープと油性ペンは危険な箇所に印を付ける際に使います。
しかし、室内側と外壁側でセルフ点検の方法は異なります。
ここでは、
- 室内側の結露セルフ点検方法
- 外壁側の結露セルフ点検方法
にわけて見てみましょう。
室内側の結露セルフ点検方法
まず、湿度計で室内湿度を計測します。その後、非接触温度計で外壁面の温度を測定して他の場所より極端に低い箇所がないか調べます。温度差が大きい箇所は、結露の可能性があるため要注意です。
次に、点検用ライトで「壁紙の浮きや剥がれ・黒ずみ・カビ」などを確認します。家具裏や壁の中央など見えにくい部分もチェックしましょう。危険箇所があればマスキングテープで印を付け、スマートフォンで撮影し記録を残します。
後日、同じ場所を撮影して両者を比較して症状の違いを調べます。進行している場合は、被害拡大の可能性が高いと判断できるでしょう。
外壁側の結露セルフ点検方法
非接触温度計で複数箇所の外壁温度を計測し、極端に低い箇所がないか確認します。塗膜の膨れ、サイディングの浮き・反り、ひび割れ、コーキングの剥がれなどをチェックしましょう。雨水の浸入が内部結露の引き金になるため、劣化箇所の早期発見が大事です。
次に、雨上がり後の晴天時に乾きにくい箇所がないか観察します。乾きにくい箇所は内部に湿気を溜め込んでいる可能性があるため要注意です。
DIY点検時は注意点がある!何に気を付けると良い?
DIY点検は現状把握には有効ですが、いくつかの注意点があります。次の3つを中心に見てみましょう。
- 高所点検時の安全確保が重要
- 壁内部の直接の確認は避ける
- 雨漏りと結露の見極めは難しい
それぞれ詳しく見てみましょう。
高所点検時の安全確保が重要
高所での点検は落下や転倒のリスクがあります。脚立などを使用する際は安定した地面で作業し、無理をしないことが大切です。
壁内部の直接の確認は避ける
壁を壊して内部を直接確認することはDIYでは避けた方が良いでしょう。無理に内部確認を試みると補修範囲が広がり、無駄な費用がかかるため危険です。
雨漏りと結露の見極めは難しい
雨漏りと結露は症状が似ているため、DIYでは判断がつかない場合も多くあります。クロスの剥がれやシミだけで原因の特定は難しく、誤った対応では被害拡大の可能性があるため要注意です。
外壁の内部結露を予防・軽減する方法がわかれば被害が小さく済む!何に気を付ければ良い?

外壁の内部結露を予防・軽減させるには、被害が進行する前の取り組みが大事です。次のことを中心に見てみましょう。
- 日常的な換気と湿度管理
- 室内湿度は50〜60%を目安に
- 建物メンテナンスによる予防策
- リフォーム時の断熱材グレードアップも検討
項目ごとにお話しします。
日常的な換気と湿度管理
外壁の内部結露は、被害が進行する前の予防が最も大切です。日常的に換気すると室内の湿度を適切に管理できるため、湿度の上昇を防げるため結露の発生率が下がります。
室内湿度は50〜60%を目安に
室内湿度を50〜60%程度に保つことが理想的です。冬場は加湿器の使いすぎに注意し、必要に応じて結露防止シートを窓際に貼り付けることで湿気の滞留を防げます。
建物メンテナンスによる予防策
外壁目地やサッシ周辺のコーキングが劣化すると湿気や水分が入りやすくなるため、定期的な点検と早めの補修が重要です。外壁塗装も適切なタイミングで行うと防水性能を維持し、湿気の侵入リスクを抑えられます。
リフォーム時の断熱材グレードアップも検討
リフォームの機会があれば、壁内の断熱材のグレードアップも検討すると良いでしょう。断熱性能を高めることで壁内の温度差を減らし、結露発生を抑制できます。
専門業者に相談するタイミングはいくつもある!いつ聞けば良い?
専門業者に相談するタイミングは次の通りです。
- 壁紙の剥がれや黒ずみの拡大
- 床下や壁の内部からカビ臭の悪化
- サイディングの浮きやモルタルのひび割れが複数箇所ある
- 室内の湿度管理を徹底しても改善しない
いずれかに該当する場合、結露の可能性が高いため専門業者への相談を検討するタイミングです。とくに、構造部分の腐朽やカビの被害も進行していると、修繕費用が膨れるかもしれません。異常を感じた時点で早めに相談することが、資産価値の維持と家族の健康を守る最善策につながります。
▼合わせて読みたい▼ |
屋根工事業者の新創が教える!外壁内部結露のセルフ点検と早期相談で住まいを守ろう

外壁の内部結露は静かに進行し、気付いた時には壁紙の浮きや剥がれ、カビ、断熱性能の低下など深刻な被害につながります。DIY点検では、非接触温度計や湿度計、点検用ライトを使い、壁面の温度差やクロスの状態をチェックしましょう。壁の浮きや黒ずみ、外壁側の塗膜の膨れ、サイディングの反りなどを見逃さないことが大切です。定期的な換気や湿度管理、外壁・サッシのコーキング補修も効果的ですが、セルフ点検で異常を発見したら、無理に内部確認せず早めにプロに相談してください。
屋根工事業者の新創では、点検・診断から必要なメンテナンス提案まで丁寧にサポート。被害拡大を防ぐため、まずはお問い合わせフォーム、メール、電話、ショールームでお気軽にご相談ください。
住まいの健康と資産価値を守るために、早期のアクションをおすすめします。
▼合わせて読みたい▼ |